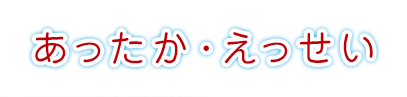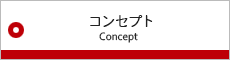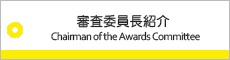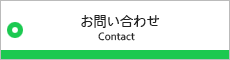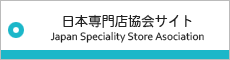- 第20回 2016年度受賞作品一覧
- 第19回 2015年度受賞作品一覧
- 第18回 2014年度受賞作品一覧
- 第17回 2013年度受賞作品一覧
- 第16回 2012年度受賞作品一覧
- 第15回 2011年度受賞作品一覧
- 第14回 2010年度受賞作品一覧
- 第13回 2009年度受賞作品一覧
- 第12回 2008年度受賞作品一覧
- 第11回 2007年度受賞作品一覧
- 第10回 2006年度受賞作品一覧
- 第09回 2005年度受賞作品一覧
- 第08回 2004年度受賞作品一覧
- 第07回 2003年度受賞作品一覧
- 第06回 2002年度受賞作品一覧
- 第05回 2001年度受賞作品一覧
- 第04回 2000年度受賞作品一覧
- 第03回 1999年度受賞作品一覧
- 第02回 1998年度受賞作品一覧
- 第01回 1997年度受賞作品一覧
退職や転居等により氏名公表許諾未確認の方のお名前は割愛させていただきました。
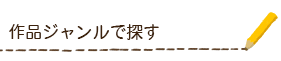

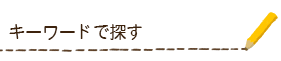
各記事には関連キーワードを設定しています。
自転車・メガネ・子供・感激…などキーワードを入力してください ※複数は(カンマ区切り)
自転車・メガネ・子供・感激…などキーワードを入力してください ※複数は(カンマ区切り)
ティータイム
第10回 2006年度 受賞作品
最優秀作品
作者名:西田葉子
所属企業:㈱大塚家具
最優秀作品
作者名:西田葉子
所属企業:㈱大塚家具
記事(紹介文)
商品をお勧めし、買っていただく。日々繰り返している「販売」というシンプルなやりとりですが、あるお客様との出来事をきっかけに私は全く新しい自分の仕事に気づくこととなりました。
残暑の厳しい九月のある日、40代くらいの女性が1人、購入されたマンションで使われる家具を揃えたいとショールームにご来館されました。私はご新居でどういう生活を希望されているのか、そのイメージをうかがいたくてお話をすすめましたが、何をうかがってもご返答をいただけません。
「例えば仕事からご自宅に戻られて、これができたらいいのに、と思われることはございませんか?」長い沈黙が続き、女性は少し困ったような表情でこうおっしゃいました。「こだわりとか希望がこれといってないのよ。あなたに任せるから好きにして、どうせ気ままな女の一人暮らしなんだし。」
後日、女性は何度かご来館されたのですが、インテリアに関しては本当にご要望を口にされず私に任されたままで、話して下さることといえば趣味で登られる山のお話ばかりでした。「山の中でお茶を飲む時間は最高よ、西田さん!」必ずといっていいほどこうおっしゃると、今度はお茶についてのお話が続くのでした。私はあまりのお話の長さに困ったな、と思うことも少なくありませんでした。
ところが家具搬入当日、偶然ご主人様の遺影を目にしたことをきっかけに、初めてその女性が1月にご主人様を病気で亡くされたばかりだということ、そして生前登山がご趣味だったご主人の代わりに、奥様であるその女性が今は山に登られていることを知りました。私はその女性に無神経な質問をしてしまったことを強く後悔しました。「家に帰ってこれができたらいいのに、と思うことは何ですか?」それがとても残酷な質問だったこと、そしてあの時の沈黙の理由を知りました。奥様はご主人様と過ごす時間を心から望まれたに違いありません。
「今までいろいろと無神経なお話をしてしまって申し訳ありませんでした」。私がそうお詫びすると女性は笑って答えました。「あなたは家具屋さんなんだから家具を勧めて当然でしょう。これからもこの部屋に合いそうなものがあったら教えてね」。
帰りの車中、私は自分の配慮の足りなさに情けないような悲しい気持ちで一杯になりながら、今自分ができることは何かを必死で考えました。そして1枚のリトグラフを取り寄せることにしました。「輝く森へ」というタイトルの、柔らかい光をいっぱいに浴びて輝く森の絵です。あの部屋で過ごす1人の時間が少しでも女性にとってやさしいものであるよう、ご主人様の大好きだった山の中にいるような安心感を味わっていただけたら、という願いからでした。
すぐに女性と連絡をとり、リトグラフをお持ちしました。箱から絵を取り出した瞬間、今までに見た最高の笑顔が女性の顔に輝きました。部屋の真ん中に置いてみると、絵の中の陽だまりがお部屋全体に広がったような、とても暖かい雰囲気になりました。微笑みながら、女性が「リビングで飲むお茶がおいしくなりそうね」。そうおっしゃったのを聞いて、自分自身の心がとても満たされていくのを感じました。それは機能としてのインテリアではなく、女性の居場所を提供できたことに対する喜びでした。
私はそれまでインテリアを販売することが自分の仕事だと思っていました。その出来事をきっかけに、お客様に満足して幸せな気持ちになっていただくことが仕事なのであって、インテリアを販売することはそのための手段だと考えるようになりました。だからこそ、いつでも最大限の幸せを引き出して差し上げられるよう、インテリアのプロでいたいと今は思っています。