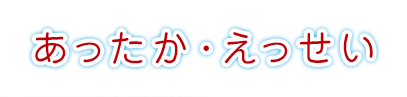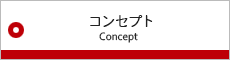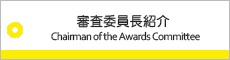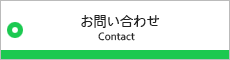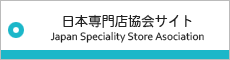- 第20回 2016年度受賞作品一覧
- 第19回 2015年度受賞作品一覧
- 第18回 2014年度受賞作品一覧
- 第17回 2013年度受賞作品一覧
- 第16回 2012年度受賞作品一覧
- 第15回 2011年度受賞作品一覧
- 第14回 2010年度受賞作品一覧
- 第13回 2009年度受賞作品一覧
- 第12回 2008年度受賞作品一覧
- 第11回 2007年度受賞作品一覧
- 第10回 2006年度受賞作品一覧
- 第09回 2005年度受賞作品一覧
- 第08回 2004年度受賞作品一覧
- 第07回 2003年度受賞作品一覧
- 第06回 2002年度受賞作品一覧
- 第05回 2001年度受賞作品一覧
- 第04回 2000年度受賞作品一覧
- 第03回 1999年度受賞作品一覧
- 第02回 1998年度受賞作品一覧
- 第01回 1997年度受賞作品一覧
退職や転居等により氏名公表許諾未確認の方のお名前は割愛させていただきました。
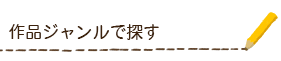

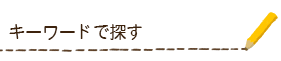
各記事には関連キーワードを設定しています。
自転車・メガネ・子供・感激…などキーワードを入力してください ※複数は(カンマ区切り)
自転車・メガネ・子供・感激…などキーワードを入力してください ※複数は(カンマ区切り)
届けられた春
第11回 2007年度 受賞作品
入賞作品
作者名:大塚真祐子
所属企業:㈱三省堂書店 神田本店
入賞作品
作者名:大塚真祐子
所属企業:㈱三省堂書店 神田本店
記事(紹介文)
木の芽があおくめぶいたころ、窓に面したスペースを使ってなにか春らしい催しを、と考えた私の頭に浮かんだのが、谷川俊太郎の「はる」という詩でした。
「はるのひととき/わたしはかみさまと/しずかなはなしをした」という印象深い一連で終るこの詩をディスプレイに使い、郊外の新刊書店ではそのコーナーさえ設けられていない「詩集」をまとめて並べてみるのはどうか、ともちかけると、いまどき詩集のフェアなどで、はたして売上げがとれるとのかという意見が上がりました。提案した私も実際のところ採算については甚だ疑問でしたが、それでもこのフェアをつよく主張しました。
自分が「いい」と思っている本が売れる本とは限らない。しかし、そういった本の存在を知ってもらい手にとってもらう、そういう時間を提供する書店があってもいい。また、この書店が何に価値を置いているかをこちらから提示することで、今後きっとその価値観に共感するお客様があらわれる、そう私は考えていました。
結果、短期間ではありますが小さなフェアを開催することに決定し、さっそく同僚とガラス窓のディスプレイにとりかかりました。まだパソコンが現在ほど普及していなかったころのことなので、ワープロで打ち込んだ「はる」の詩を拡大コピーし、背景に辛夷の花を手作りしました。ワイヤーと白い布を使って空の写真の上に貼り付けると、不恰好で安上がりながら、青と白のコントラストが春らしい、それなりの見栄えになりました。
ある日、母娘とおぼしきお客様が店を訪れ、窓から見える辛夷の花と詩のディスプレイを1日だけお借りできないだろうか、とおっしゃいました。近くの斎場で、明日おじい様のお葬式があるのでこちらに来たところ、あのディスプレイを見つけてとてもいい詩だと思ったので、ぜひ遺影のちかくに飾らせてほしい、とのお話でした。快諾すると、娘さんが喜んで「はる」の入っている谷川俊太郎詩集をお買い上げくださいました。
たった1冊の売上げですが、私にはそのいきさつと共に何より重みのある1冊でした。1冊の本のひとつの詩が、私の想像をこえた所へ届いたことをうれしく思うと同時に、身の引き締まるような気持ちも覚えました。販売する側にとっては何百冊のうちの1冊でも、その1冊を手に取った人にとっては唯一なのだということを改めて感じました。
母娘はあくる日喪服でご来店され、どこからどう見てもやはり稚拙な辛夷のディスプレイを、大事そうに布にくるんで返しに来てくださいました。いいお葬式になりました、と静かに笑って、帰られました。
日々出版される大量の書籍と、それに伴う業務に追われて忘れがちですが、本との出会いをプロデュースすることは書店員にとってもっとも大事な仕事のひとつだと私は考えています。聞いてみればいくつもの世界があらわれる「本」を届ける仕事に、自分が関わっていることを誇りに思うとき、私はもう顔も覚えていない母娘のことと、白布の辛夷のことを思います。